60代・70代の平均貯蓄額2024!平均値・中央値と貯金なしの家計の貯蓄方法

老後(60代、70代)の平均貯蓄額は、現役世代とは違う傾向があります。仕事の有無やお金が入る仕組みがあるか、これまで貯蓄したかなどで個別に大きな違いがでてきます。
■この記事で学べること
【1】60代・70代の年収別の平均貯蓄額(平均値・中央値)
【2】年収別の貯蓄額ゼロの割合
【3】1,000万円、3,000万円を貯蓄している年収別の割合
【4】独身の平均貯蓄額(平均値・中央値)
【5】老後(60代・70代)からの貯蓄方法は?
家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和6年)の調査結果(2024年12月公表 最新)を元に、老後(60代・70代)の貯金事情と家計について解説します。
*一部単身世帯(独身)のデータも掲載しています。
※こちらにご登録頂くと「Mylife Money Online」の記事だけでは読めないお得なお金の情報を定期的にお届けいたします。
この記事のもくじ
老後(60代・70代)の年収別の平均貯蓄額の平均値と中央値

最初に定年後の老後世代の平均貯蓄額について、60代と70代の年収別に「平均値」と「中央値」を確認しましょう。
貯蓄の平均とは全体を平均したものです。
但しごく一部の貯蓄の高い人がいると平均はそれに引きずられて高くなります。
中央値はすべての統計の数字を並べたときに真ん中にくる数字の統計も入れています。平均貯蓄額を見るときには中央値の方がしっくりくるはずです。
そのため中央値を基準に平均貯蓄額の参考としてください。
※平均貯蓄額の統計には総務省の家計調査報告もありますが、J-FLEC(金融経済教育推進機構)の調査が年代・年収別で掲載されているのでこちらを使っています。
60代の貯金額の平均と中央値
60代(還暦後)の貯蓄額は、年収別には下記の結果となりました。
| 年収 | 平均値 | 中央値 |
| 収入なし | 402万円 | 0万円 |
| 300万円未満 | 1164万円 | 200万円 |
| 300~500万円未満 | 1602万円 | 500万円 |
| 500~750万円未満 | 1752万円 | 900万円 |
| 750~1,000万円未満 | 3394万円 | 1510万円 |
| 1,000~1,200万円未満 | 2799万円 | 1680万円 |
| 1,200万円以上 | 5317万円 | 2950万円 |
*出所:J-FLEC(金融経済教育推進機構) 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 2024年調査結果の統計を元に筆者作成
還暦を迎えた60代以降になると会社員などだと定年で収入無しの人が増えます。
一方で自営業やオーナー企業の会社役員などはそのまま収入が継続します。不動産収入などがある人も同様です。
70代の貯金額の平均と中央値
70代については「70代以上」となっているので80代以降の方も統計に入っていると考えてください。
70代以降の貯蓄額の平均値は、年収別には下記のようになっています。
| 年収 | 平均値 | 中央値 |
| 収入なし | 24万円 | 0万円 |
| 300万円未満 | 817万円 | 145万円 |
| 300~500万円未満 | 1610万円 | 800万円 |
| 500~750万円未満 | 3030万円 | 1475万円 |
| 750~1,000万円未満 | 3110万円 | 1600万円 |
| 1,000~1,200万円未満 | 3129万円 | 2650万円 |
| 1,200万円以上 | 6682万円 | 3725万円 |
*出所:J-FLEC(金融経済教育推進機構) 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 2024年調査結果の統計を元に筆者作成
高齢者である70代の貯金額は年収別にはこのようになりました。
60代と平均を比べると貯金が増加しているところもありますが、資産の取り崩しをするご年齢なので大きな60代と比べて大きな乖離はありません。
定年後の高齢者(60代・70代)の年収別の貯蓄額ゼロ(なし)の割合

老後の世代だと少々深刻な話になりますが、60代、70代でも貯蓄ゼロ(なし)の人がいます。
老後に貯金がないというのは良くない状態ですが、まずは統計結果をみてみましょう。
統計上は、「金融資産非保有」という項目になり、貯蓄ゼロの人の年代・年収別の「割合」になります。
60代の貯蓄額ゼロ(なし)の割合
| 年収 | 貯蓄なし |
| 収入なし | 62.52% |
| 300万円未満 | 30.00% |
| 300~500万円未満 | 23.00% |
| 500~750万円未満 | 13.90% |
| 750~1,000万円未満 | 12.20% |
| 1,000~1,200万円未満 | 7.70% |
| 1,200万円以上 | 5.60% |
*出所:J-FLEC(金融経済教育推進機構) 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 2024年調査結果の統計を元に筆者作成
年収300万円未満、収入なしを見ると、それぞれ30%、62%が貯蓄なしで厳しい状態です。
70代の貯蓄額ゼロ(なし)の割合
| 年収 | 貯蓄なし |
| 収入なし | 53.80% |
| 300万円未満 | 33.00% |
| 300~500万円未満 | 16.90% |
| 500~750万円未満 | 11.90% |
| 750~1,000万円未満 | 13.60% |
| 1,000~1,200万円未満 | 10.00% |
| 1,200万円以上 | 5.30% |
*出所:J-FLEC(金融経済教育推進機構) 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 2024年調査結果の統計を元に筆者作成
いまの70代であれば年金の受取をしている人がほとんどです。
働いている人もいるでしょうが、収入のない人の半数以上が金融資産を保有していません。
但し、高齢になると生活費として貯蓄の取り崩しに入っていることや残さずに使うという考え方もありますから、ここは一概には言えません。
但し平均寿命は延びているのでそれも考慮する必要はあるでしょう。
60代でも70代でもそれなりに所得があっても貯蓄ゼロの人が一定いることがわかります。
収入は高いに越したことはありませんが、それだけでもないということです。
1,000万円、3,000万円を老後に貯蓄している人の年収別の割合

ここでは60代、70代で1,000万円、3,000万円貯めている人の年収別の割合をみてみましょう。
さすがに70代になると貯蓄の取り崩しの時期にも入ってくるので減ってきています。
1,000万円を老後に貯めている人の年収別の割合
【60代で1,000万円貯蓄のある人】
| 年収 | 貯蓄1,000-1,500万円未満 |
| 収入なし | 7.50% |
| 300万円未満 | 6.50% |
| 300~500万円未満 | 8.60% |
| 500~750万円未満 | 10.60% |
| 750~1,000万円未満 | 7.30% |
| 1,000~1,200万円未満 | 11.50% |
| 1,200万円以上 | 12.70% |
*出所:J-FLEC(金融経済教育推進機構) 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 2024年調査結果の統計を元に筆者作成
【70代で1,000万円貯蓄のある人】
| 年収 | 貯蓄1,000-1,500万円未満 |
| 収入なし | 0.00% |
| 300万円未満 | 9.00% |
| 300~500万円未満 | 11.20% |
| 500~750万円未満 | 10.90% |
| 750~1,000万円未満 | 15.20% |
| 1,000~1,200万円未満 | 10.00% |
| 1,200万円以上 | 5.30% |
*出所:J-FLEC(金融経済教育推進機構) 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 2024年調査結果の統計を元に筆者作成
60代及び70代以上について特に働く時間を伸ばす必要がでてきている以上、収入金額はともかく特に60代であれば貯蓄は増やしておきたいところです。
1,000万円以上となるとやはりある程度は収入に比例してきます。
3,000万円を老後に貯めている人の年収別の割合
【60代で3,000万円貯蓄のある人】
| 年収 | 貯蓄3,000万円以上 |
| 収入なし | 2.50% |
| 300万円未満 | 11.00% |
| 300~500万円未満 | 14.10% |
| 500~750万円未満 | 19.60% |
| 750~1,000万円未満 | 34.10% |
| 1,000~1,200万円未満 | 32.70% |
| 1,200万円以上 | 46.50% |
*出所:J-FLEC(金融経済教育推進機構) 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 2024年調査結果の統計を元に筆者作成
【70代で3,000万円貯蓄のある人】
| 年収 | 貯蓄3,000万円以上 |
| 収入なし | 0.00% |
| 300万円未満 | 6.40% |
| 300~500万円未満 | 11.70% |
| 500~750万円未満 | 28.20% |
| 750~1,000万円未満 | 34.80% |
| 1,000~1,200万円未満 | 50.00% |
| 1,200万円以上 | 57.90% |
*出所:J-FLEC(金融経済教育推進機構) 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 2024年調査結果の統計を元に筆者作成
3,000万円以上貯金出来ている人の割合ですので、3,000万円以上と考えてください。一般的に年収が上がるにつれて3,000万円以上貯金のある人の割合が増えていきます。
他の若い世代でも似た傾向がありますが違うのはその比率が高いところです。
これは60代、70代ともに同じ傾向があります。
60代・70代独身の平均貯蓄額の平均値と中央値
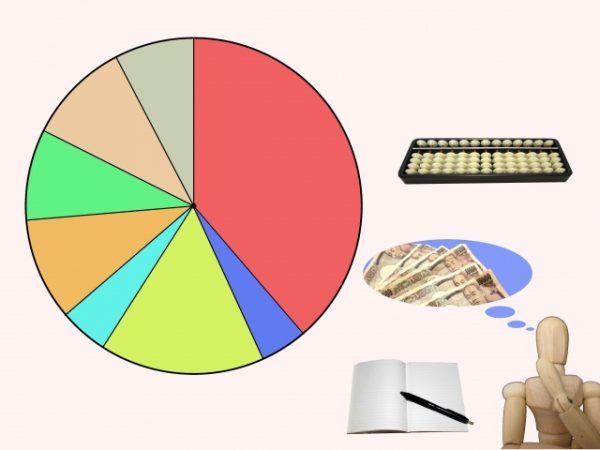
J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査」の統計には二人以上世帯と単身世帯のものがあります。
2人以上世帯については60代70代とも夫婦のみのこともあれば、親と子あるいは2人以上いるケースもあると考えてください。
ここまでの統計は二人以上世帯のものをみてきました。
ここでは単身世帯、つまり60代・70代の独身の人の収入別の統計(平均値・中央値)をみておきます。なお、性別では分かれていません。
【60代の独身の年収別の平均貯蓄額(平均値・中央値)】
| 年収 | 平均値 | 中央値 |
| 収入なし | 861万円 | 50万円 |
| 300万円未満 | 1083万円 | 168万円 |
| 300~500万円未満 | 2427万円 | 948万円 |
| 500~750万円未満 | 4626万円 | 2450万円 |
| 750~1,000万円未満 | 2771万円 | 2100万円 |
| 1,000~1,200万円未満 | 0万円 | 0万円 |
| 1,200万円以上 | 1150万円 | 1150万円 |
*出所:J-FLEC(金融経済教育推進機構) 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 2024年調査結果の統計を元に筆者作成
独身の人は自分で何とかしなければならないので、どの年収層でもそれなりに貯蓄額はあるようです。
【70代の独身の年収別の平均貯蓄額(平均値・中央値)】
| 年収 | 平均値 | 中央値 |
| 収入なし | 269万円 | 0万円 |
| 300万円未満 | 975万円 | 300万円 |
| 300~500万円未満 | 3217万円 | 1600万円 |
| 500~750万円未満 | 7356万円 | 6000万円 |
| 750~1,000万円未満 | 12983万円 | 14950万円 |
| 1,000~1,200万円未満 | 625万円 | 625万円 |
| 1,200万円以上 | 6749万円 | 5700万円 |
*出所:J-FLEC(金融経済教育推進機構) 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 2024年調査結果の統計を元に筆者作成
70代の単身世帯の数字ははじめてでてきましたが年齢的なものかそれなりにあります。
年収1,200万円以上は、この統計ではめったにみない億越えとなりました。中央値が平均値より高くなっていますが実際の統計もこのとおりです。
老後(60代・70代)からの貯蓄方法は?

60代、70代の定年世代、ここまでの統計を見てみると、結構貯金がある人もいれば、貯金ゼロ(なし)の人もいて、他の世代よりも差がでています。
老後から貯金する方法はというと、この世代から新たに何かをはじめるにはエネルギーがいるので出来る人は少ないかもしれません。
働ける人、仕事のある人は就業して、家計を管理して無駄を減らすことが基本です。
収入と支出の把握は家計管理の基本です。
年代を問わずここが分かっていないと貯蓄しようがありません。毎月何とかなっているからいいのではなく、収入と支出が把握できてないから貯まらないのです。
その上で無理のない範囲で殖やすことも考えてみましょう。
筆者のお客様に60代で自営業を辞めてから株式投資を独学で始められた方がいました。
うまく儲けがでたこともあれば、うまくいかなかったこともあったようですが、悲観的ではなく、楽しそうに話しをされていたのが印象に残っています。
株主優待でお孫さんとディズニーランドに行くのを楽しみにされていました。
投資に関して高齢の方でやってはいけないのは、分からないとかめんどくさいを言い訳に人に丸投げすることです。
相談するのはどんどんしたらいいでしょうが、相手の言いなりに任せてしまうくらいならやらない方がいいでしょう。
他にも後期高齢者を過ぎて元気に働いている人もいました。
なおこの方は会社役員などではなく普通にお勤めです。
例えば老後に入ってから株式などで投資をゼロからはじめるのは勉強や本人の意思が必要です。
必ずしも勧めませんが、ご本人にそのつもりがあればむしろ良いことだと思います。
一発逆転などという発想はせずに働けるなら可能な範囲で地道に収入を得つつ、何かはじめようと思うならしっかり準備してください。
まとめ
60代・70代の平均貯蓄額2024年12月最新!平均値・中央値と貯金なしの家計の貯蓄方法、についていかがでしたか。
平均貯蓄額について、全体の数字と年代(20代、30代、40代、50代、老後(60代・70代))と別々にみてきました。
世代ごとに特徴がありますし、また老後といっても今の現役世代が老後を迎えるころには、税金や社会保障なども大きく変わっているでしょう。
現役世代の人はいまからできることを地道に進めてください。老後といっても定年直後とその後ではやはり色々変わります。
老後世代でも家計管理は必須です。家計の支出がザルになっているなら今からでもしっかり改善してください。
またこの統計は主に二人以上世帯(収入からの貯蓄割合は独身も)なので、夫婦のパターンが比較的多いでしょう。
年代別ではありませんが、独身のデータが関連記事にある平均貯蓄額の記事の中になるので参考にしてください。
※こちらにご登録頂くと「Mylife Money Online」の記事だけでは読めないお得なお金の情報を定期的にお届けいたします。
